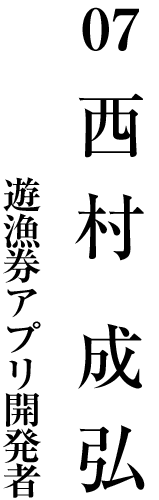
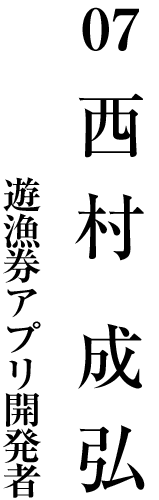
川はいつまでも同じではない
内水面(河川や湖沼)の漁業協同組合は、漁業で生計を立てる人たちで組織される海のそれとは異なり、おもに遊漁や魚の保護・増殖を管理する団体である。
レジャーとして釣りを楽しむ人から遊漁料を徴収し、そのお金で魚の放流資金や活動費をまかなっている。組合員の多くは流域で生活し、釣りや漁を楽しみながら生活している人たちだから、一般釣り人と同様に組合にお金を納めている。
以前はこのようなシステムでうまく管理・運営できていた河川の遊漁(おもにアユや渓流魚であるヤマメ、アマゴ、イワナなどの釣り)だが、近年はきわめて厳しい状況にある。
組合員の激減と高齢化、そして釣り人の減少で収入が減り、赤字経営の小規模な組合が多い。組合員は漁業で生計を立てているわけではないので、ボランティアのようになりつつある活動にも限界があり、漁協を解散したという話もよく聞かれるようになった。

漁協がなくなっても川は流れ続ける。放流が途絶えても天然魚の再生産が期待できないわけではない。だが、いつまでも川が同じであるとは限らない。
たとえば間接的な漁協の役割のひとつに河川環境の監視がある。魚が生きる上で不適切な河川工事などがおこなわれないよう、一定の抑止力を発揮できるからだ(できていないことも少なくないが)。
つまり漁協がなくなれば放流がなくなる、あるいは無料でいつでも自由に釣りができる、という単純な問題ではなく、川が“無法地帯”と化す恐れもある。
スマホから遊漁券が買えるアプリケーションサービス「フィッシュパス」を生み出した西村成弘さんが生まれ育った集落を流れる竹田川も、まさにそんな問題に直面していた。
ITで起業を夢見ていた
「生まれは福井です。今は人口300人くらいの丸岡町竹田地区で、私が住んでいた頃は800人くらいいたんですけど、今で言う限界集落ですね。50%以上の方が60歳以上なので、経済指標でいえば成長できる地域ではないということになっちゃいます」
「爺ちゃんにヤマメ、イワナ釣りに連れて行ってもらったのが原点です。毛針を使ったり極端な話、手づかみとか追い込んで網で獲るとか、そういったことをやってましたし、遊ぶことはそれしかないんですよね。ちょうど小学生くらいの記憶です。1学年9人の学級だったんですが、まだ多い方だったんですよ。その下が5人で上は8人でした」
高校入学を機に市内に出た西村さんはバンド活動に夢中だった青春期を経て、関西大学文学部に進む。「ベタベタの学生生活を送ってやろう」と、テニスサークルに入ってバイトにも精を出し、海外をバックパッキングで放浪もした。卒業後は液晶フィルムなどを扱っている化学メーカーに就職する。

「英語とドイツ語ができたので海外事業部に3年くらいいたんですけど、当時2000年の前後はITバブルだったんです。在学中からITで起業したいと思っていましたが、深い考えがあったわけではなく『変わった行動をする人間は社会に適合できないから社長になったら?』という話を真に受けて(笑)」
ITで独立するにはどうしたらいいかを考えているとき、サンドイッチのワゴン販売で儲けてからITで起業するという伝説的な話を経済誌で読んだ。いきなり飲食業の世界に飛び込むのは怖かったので、企業に入って勉強してから独立しようと思っていた。
「3年勤めて飲食を起業しようと思ったとき、ちょうど讃岐うどんブームだったんです。東京でやろうと思ったら地代が100万、こっちは10万ですよ。独立する前に飲食のコンサルタント会社にもいて、そこで数字の作り方も分かった。結婚相手もいたから福井へ帰ってFC(フランチャイズ)をやろうと。地元ですし地域に根ざして商売できると思ってましたから一気に3店舗くらい出しました」
紆余曲折ありながら現在も5店舗を経営。そこに至るまでの間、あまりにも多忙でITのことはすっかり忘れていた。ふるさとの竹田川のことも……。
Amazonで遊漁券は買えないんですか?
釣りどころかITで起業を夢見たことも、すっかり昔の話になっていた。
「ガラケーでしたもん。もっと言えばスマホは買ったんですけど、ポケットに入れておくと勝手に電話がかかっちゃうし、1週間で戻したくらいです。そのくらい音痴だったんで」
仕事が落ち着いて部下も育ってきた頃、ふと昔みたいに釣りに行こうと思った。しかし、竹田川で竿を出した西村さんはがく然とする。
「山は荒れ果てているし、川は浅くなっているし『ここ、飛び込めたはずだぞ!?』と。中学まで竹田にいたので約30年ぶりですかね。ヤマメやイワナがめちゃくちゃいた場所が変わってしまって『何だこれ……』と。昔、橋の上から石をぶつけて拾ったほどいたウグイもいない」
タイミングがよかったのか悪かったのか、そのとき監視員が見回りに来た。当時は遊漁券が必要なことを知らなかったが、その監視員は幼なじみの友人のおじさんで組合長になっていた。
「おお、エーサイ(西村さん)か。ひさしぶりやな、釣りしとるんか。遊漁券は?」
「遊漁券て何ですか?」
「釣りするために必要な券や」
そのとき西村さんは言った。
「Amazonとかで買えないんですか?」

「アホか、と言われて(笑)。『でもおまえも組合員やな』と。は? という話ですよね。爺ちゃんが組合員だったので、父、僕と自動的に(権利が)受け継がれていたんですが『組合員て何ですか?』みたいな」
趣味探しから地域活性化へ
ちょうどその頃、趣味探しをしていた西村さん。城めぐりや茶道をやってみたり、学生時代を思い出してテニスも再開してみたが、何かが違うと感じていた。
「福井県立大学の大学院に行く選択肢もあって、10年間経営をやってきたので理論を整理するために行ってもいいな、と思っていたんですが、何かテーマが必要だったんですよ。じゃあ、竹田の地域活性化を大学でテーマとして勉強してみようかと」
「それで大学院は通ったんですけど、担当教授に内水面の現状をふまえて経営的なことをやりたいと提出したら、それはNG。水産学部がやることだと。地域活性化や経営の視点で内水面を見ることが今までなかったんです。それで駅前の商店街を復活させましょう、というテーマをやっていたんですが、それはそれで意義があるにしても、つまらないじゃないですか(笑)」
釣りを再開してから岐阜にも足を運ぶようになったが、「この問題は竹田川だけじゃないよな」と、より強く感じるようになった。そんなとき「福井発!ビジネスプランコンテスト」というベンチャー企業を創出するイベントがあり、授業でレポートにするためそのセミナーに参加した。

「会場で『あなたのアイデアをビジネスプランにしてみたらどうですか?』という用紙があったので、遊漁券という釣りで必要な紙の券をAmazonで買えるようにした方がいい、みたいな内容で書いて出したら、事務局の方に『これおもしろいから掘り下げて正式に申請してみたら?』とすすめられたんです」
アンケートをとって釣り人の遊漁券を購入の割合、購入の義務を知ってはいるけど買えなかった割合などを調べていくうちに「あれ?」と西村さんは気付いた。
「利便性の問題が見えてきて、スマホで24時間川の状況を見て券を買えるようなものがあればいいのではないか、という企画書を出したんです」
その企画が通り、本戦でプレゼンテーションをすることになる。
「5分間のスピーチだったんですが人前で話すのは初めてですし、当時はスティーブ・ジョブスみたいなレベルじゃないと人前に立ってはダメなのやろうな、という意識があったんです。1分間でしゃべるのは300文字。なので1500文字の原稿をバチッと決めて完璧にスラスラ言えるようになってから……256回練習しました」
「人前に立つと動じてしまってうまくいかないので、最初は家族の前で、次はショッピングモールの入り口で精神的に耐える練習をし、最後は福井駅前の横断歩道で……怪しい人でしたけど(笑)」

努力の甲斐があって結果は見事グランプリ。新聞にも記事が掲載されたのだが……。
「実は、大学院に行ってることを妻には言ってなかったんですよ(笑)」
まさかの成果率150%
しかし、この時点の西村さんは企画を実現化するつもりがあまりなかった。
「そこで終わるつもりだったんです、本当は。ゴールに向けて一生懸命やるというだけで……。でも市の補助金が出たので竹田川の遊漁券が買えるアプリを開発しました」
フィッシュパス立ち上げ時のメンバーはふたり。大学院の68歳の同級生とスタートしたが、実質的には西村さんひとりだった。

もちろんシステム開発などできないので、現在も入居するビルの6階にある会社に依頼した。サービス開始は2017年3月。利用者の声に応えてクレジット決済だけでなくコンビニ決済も導入した。
「竹田川でやり始めたら、むちゃくちゃ売れたんですよ。1.5倍くらい。150%。そんなに売れるとは思わなかったです」
竹田川は渓流釣りが主体でデジタル遊漁券との相性もよく、自然再生能力もまだ残されていたので、伸びる要素があったのだと西村さんは言う。
竹田川の実績を九頭竜川で
これでいいかな、と思っていたという西村さん。しかし今度は九頭竜川の勝山漁協から「おもしろい話を聞いたんだけど」とオファーがある。
「規模が違いますからね。『ええっ、九頭竜川さんですか……対応できませんよ』みたいな話をしていて(笑)。漁協理事は70歳以上の方が多くてGPSなんて言葉を使ったら分からないですし、当時スマホの普及率も半分くらい。ひとりひとりに挨拶に行って説明しました」
「それで勝山もやり始めたんですけど、まだ市場としては様子見なんですよね。フィッシュパスは早朝から竿を出すこともある渓流釣りで抜群に効果を発揮するんですが、勝山はアユから始めたんです。アユ釣りはオトリが絡んできますのでオトリ屋さんを証明するような画面も用意しなければいけないし(※フィッシュパスは遊漁券の購入店を指定できる)、店側の確認方法も整備しなければいけない」

「結果は、解禁日に400人の釣り人が入ったのですが、使っている人は2%。『あかんわな』という話になるじゃないですか。そのときは本当にこの事業をやめたいと思いました(笑)」
そこからが「しんどかった」。少しでも使ってもらうために、説明と改良を繰り返す。偏光グラスをかけていると画面が見えない問題を解決したり、年輩の方でも使えるように病院の受け付け機や銀行のATMを見に行ったりもした。
「今では大反対した人が今はいちばん応援してくれてます。『フィッシュパスで買え』と。アユの場合オトリだけは店で買うことになるのですが、ほぼ接触しなくていいし、現金を扱わなくていい。2年くらい経ったときがコロナだったんですよ。急激に伸びたのはそれからですね」
感染したくないから販売店をやめるという声もあったが、漁協としては窓口である販売店を減らしたくない。そこで「フィッシュパスで名前だけでも残さんか?」と猶予期間を設け、積極的に動いてくれたのだ。
デジタル遊漁券のビジネスモデル
ちょうどこの頃、水産庁に遊漁券を電子化、キャッシュレス化しようという動きがあった。その一貫で補助金制度が設けられ、フィッシュパスの事業はさらに伸びる。スマホ利用率は90%を超え、同業他社も出始めて漁協側の知識も増えた。
国がそういった事業を後押しすると、県の水産課、その下の内水面漁連へとトップダウンで落ちてくる。県全体でフィッシュパスを導入する流れも生まれ、福井、三重、香川で実現。県内共通遊漁券という形では青森、秋田、新潟、栃木で。今では国が発行する補助金の資料にフィッシュパスのシステムが載っていたりと、まさに追い風に乗っている状態だ。

しかし、ビジネスは赤字経営の続く漁協が相手であり、市場規模としても限界があるように見えなくもない。
「市場規模が小さいというのは、おっしゃる通りです。パイが決まっている。まだ利用者も33万人くらいで、今は想像力を働かせながら、こんなお客さんいねんかなと、将来的なことも考えています」

昔のような川を取り戻せたか?
現在のようにフィッシュパスがここまで大きくなることを、経営者としての西村さんは想像していただろうか。
「してないですよ。それに僕は基本的にアイデアを出したというわけではなくて、しいて言えばAmazonで券が買えないかという話だけでした。あとは『どう思いますか?』という形で相談して、いろんな人が応援的にアイデアをくれたので、それを整理しただけなんですよ」
「でも知らなかったというのが逆によかった、と思うことが最近ありまして、魚が好きで川をよくしたいという思いはありましたけど、釣りそのものに関してはまっさらの状態なので、みなさん教えてくれるんですよね。ただ、漁協さんをドラスティックに改善するためにデジタルとかICT(情報通信技術)は外せないので、そこの素地は作ったなと思います」

会社としては順風満帆だが、西村さんに少し意地悪な質問をしてみた。子供の頃に遊んだような川を取り戻せた実感はありますか、と。意外にも戸惑いはなく即答だった。
「ないですね、実は。結果的に言うと売り上げも上がって黒字化していって、始めたときよりも2倍くらいになっているんです。お客さんが増えて漁協の経営も安定化しているというのは数字的にはいいんですけど、魅力的な川かどうか、昔みたいな川かどうかというとまた課題があって、いっぱいお客さんを呼ぶだけではダメだと」
事業を進めれば進めるほど、遊漁者が本当に楽しめるルールや天然魚を保護するためのゾーン設置、あるいは産卵場整備などをしないと永続的に川を守れないと身にしみて感じた。「結論から言えば道なかば」と西村さんははっきり言った。
点をつなぎ、誰とも異なる道を歩む
だからこそ、今後の課題と目標は見えている。
「そもそも川は美しいもの、守らなくちゃいけないもの、というのはみんな分かっているんですよ。でも調べると遊漁券を買わなくちゃいけないということを知っている人が4割。6割が知らないといいますし、今こういった悲惨な状況があったりして漁協がどんどん解散し、川が放置されているということを知りません」
当初は地元の川やその周辺だけのことを考えていたが、たとえ事業がうまくいったとしても漁協の解散に追い付かないと思い至った。そして遊漁券や川の現状を知ってもらうための、最短で最大のパフォーマンスが何かを考えた結果が株式上場だった。

30年ぶりに訪れたふるさとの川で受けた落胆は、しかし、西村さんをかつて憧れたITで起業する夢に引き戻すきっかけにもなった。
それは西村さんが初めてのスピーチで意識したスティーブ・ジョブスの「先を見て“点をつなげる”ことはできない。できるのは過去を振り返って“点をつなげる”ことだけだ」という言葉を、そのままなぞっているかのようでもある。
「意外にも魚ファーストの部分はぶれていない」という異色の経営者は、2025年の東京証券取引所グロース市場(高い成長可能性を有する企業向けの市場)への上場を目指し、着実に、しかし誰ともちがった道をたどりながら、その歩みを進めている。
